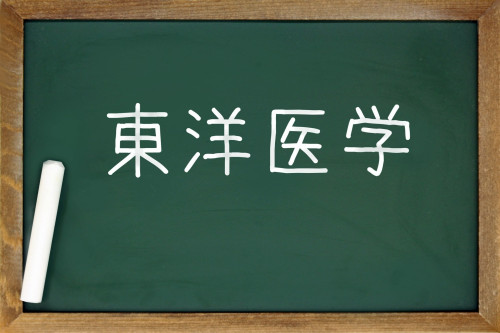ブログ
整体院? 整骨院?
前回は整体に関して触れてみましたが、今回は『整体院さん』と『整骨院(接骨院)さん』に関してです。
一般ユーザーの方でも、様々な施術院に通院経験がある方でしたら何となくお分かりかも知れませんが、未経験の方や経験が少ない方には両者の違いはかなり分かりづらいかもしれませんね?
だいいち名称からして「整体(体を整えると書きますね)」「整骨(骨を整えると書きますね)」ですから。
なんかどう考えても同じようなもの…という印象しか受けませんね。
では簡単(?)に説明してみますね。
【整体院】
①整体(系)の手技を行う(手技は統一されたものでは無いので、院によって違ったり似通ったりです)
②料金は完全自費。
③「整体」という国家資格(公的資格)は日本にはありません。
国家資格所持者(柔道整復師、鍼灸師、按摩指圧マッサージ師、理学療法士、作業療法士など)
非保持者(〇〇協会や〇〇スクールなどの民間資格を含む。いわゆる無資格者と呼ばれる)
このように整体業界では施術者により二分されています。
むかしは整体業界は圧倒的、というかほとんどの施術者は国家資格所持をしている方は少なかったんですが、近年は資格所持者の参入組が増えて来ている傾向にあります(その割合は不明です)
ちなみにワタシも国家資格所持者の参入組の方です。
こう書いてみますと整体界隈は意外と単純かも?
施術内容は別としてですけど。
次に【整骨院(接骨院)】
①院名に「整骨院」と「接骨院」と表記されていて「何か違いはあるの?」と思われた方はいらっしゃいます?
意味としてはどちらも一緒です。
法令的には「接骨院」が望ましいようですね…。
まぎらわしいからどちらかに統一すれば良いのに~と思うんですけど。
②「整骨院(接骨院)」を標榜出来るのは施術者(院の代表者)が「柔道整復師(略して柔整師)」の国家資格所持者のみです。
従業員はこの限りではありません。
で、みなさんご存じの方は少ないと思いますが、この整骨院と柔整師さんの本来の業務は「骨折、脱臼の応急処置、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)」などの「怪我の処置」となっています。
以前は接骨院の名称を使うところがほとんどだと思いましたが、近年は整骨院の名称が多くなっているようですが(どちらの割合が多いかは知りませんが)「接骨」の方が「骨を接ぐ」というと折れた骨の手当みたいで分かりやすいではないですか?
つまり肩こりや腰痛などは本来の業務では無かったんですね。
学校(養成機関)でも勉強するのは主となるのは外傷に関してであり、他の疾患に対しての勉強は少ないです。
外傷以外に関する勉強は各自でセミナー(講習会)に参加したり、職場で教えてもらうか独学などで勉強しているわけです。
③現在、料金体系は以下のようになっています。
1,健康保険適応(労災、交通事故含む)
上記の怪我(外傷)のみが保険適応であり,いわゆる普通の腰痛や肩こり等の慢性症状は非対応です。
ちなみに「骨折、脱臼は応急処置は保険可ですが、それ以降は医師の同意が必要」となります。
現在、保険適応のみで行っている整骨院(接骨院)さんは少ないのではないでしょうか?
詳しくは知りませんが…。
2、健康保険抵抗+自費施術
外傷に対しては健康保険を使用し、慢性症状(肩こりや腰痛等)に対しては自費で施術を行っている院さんです。
本来、こうあるべきでしょう…慢性疾患にも施術するのであれば。
このタイプの院さんが現在は一番割合的には多いのかも?
3,完全自費
つまり外傷(怪我)を扱わないので健康保険は使わずに、主に慢性症状を対象とした施術を行っている院さんです。
しかしこうなると整骨院と標榜していても、中身は整体院と変わらないんじゃないかと思いますが…?
【なぜ柔道整復師には柔道という武道の名称が入っているのか?】
それは、整復術という外傷に対しての施術法の起源が柔術などの武術にあった為です。
柔術などの武術は「殺法(さっぽう)」→敵を倒す 「活法(かっぽう)」→怪我の処置方法の両面がある為です(簡単に云うと)
明治時代に柔道という武道が柔術を基に創始され、全国的に拡がり柔道家が増えました。
彼らは道場経営の傍ら、外傷の手当などを行っていましたがそれも食い扶持のひとつだったんですね。
後に資格化された時に結果、柔道という冠をつけることになったようです。
【なぜ整骨院(接骨院)でも整体院のようなことを行うのか?】
40~50年位前(これはワタシの記憶と経験です)などは、巷には整形外科のクリニックなどあまり無くて(特に田舎の方では)部活動などやっていた生徒がちょっと捻挫したり、肉離れなどすると接骨院に通院して電気治療を受け、包帯巻いてもらって固定したり…そんな感じでしたね。
大人でも腰や膝などを痛めて通院したりしていました。
(ほんとはこれ、怪我でなければ保険適応外なんですけど…はい)
その後、段々と街にも整形外科が増えてくると外傷で接骨院に通院する患者さんが当然減って来るわけです。
なんといっても整形外科だとレントゲンや血液検査など必要な検査も出来る、薬も処方出来るし病院でしたら手術も出来る。
接骨院では検査は出来ないのでは触ったり、見た目でしか判断出来ませんから信頼度も違いますわね。
まぁそれでも昔は現在と違い、怪我の処置に長けている先生がけっこういらっしゃったものです。
包帯巻きや固定処置でも病院でやってもらうより上手だったりしてね。
今ではそのような先生はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか?
学校では知識は覚えられても、実際に外傷の患者さんをみて処置する技術は覚えられない。
接骨院(整骨院)に勤務してもあまり外傷の患者さんは来院されないし、おそらく院長や先輩の先生にしてもほとんど経験ないでしょう?
外傷の患者さんが来院されないとなると院の経営としては、他の症状の患者さんに来院してもらわないと困るわけですね。
すると当然ですが外傷のように急性症状の患者さんでは無く、慢性症状の患者さんに通院して頂く以外に無い。
それで以前から腰痛で腰に電気をかけたり、ちょっとマッサージをしたりの施術を行っていたわけです(鍼灸院を併用している院もけっこうあります)
近年ですと骨盤矯正(産後)やら姿勢矯正やら、美容系からダイエット系までメニューを増やしたりして…ね。
このように施術のメニューだけをみてみると、整骨院も整体院もほとんど同じように思えますね。
一般の方には区別がつきにくいでしょう?
結果こう書いてみますと、整骨(接骨)業界が複雑?に思えて来ましたよ、はい。
では整体は?
前回は整体は東洋医学か?がテーマでしたが。
「違います」ということで。
では、なんだ?と。
はい、ところで「整体」という言葉は聞いたことがあるという方はわりといらっしゃることでしょう?おそらく。
しかし、「整体とはこういうものだ」と理解されている方はほとんどいらっしゃらないのでは?
せいぜい”このようなものかな?”と漠然としたイメージだけではないでしょうか?
【整体とは】
じつは整体の定義ってないんですよ。
整体とはこうだ…という統一された手技もありません。
ちなみに整体を検索してみましたら「背骨や骨盤の歪みを整える」「筋肉や骨格のバランスを整える」など記載されるケースが多いですね。
一般の方も整体に対してこのようなイメージをお持ちの方も一定数いらっしゃるでしょう。
そうですね~、たしかにそういう面もありますね。
しかし、そうとばかりも言えないですし、定義というほどでも無いかと。
ワタシは「整体」とは…「整体系」というのが正しいのではと考えます。
つまり単純に『属性、カテゴリー』を表しているだけの名称です(全くの私見です)。
例えますと、「整体」という名前の箱(枠組み)がありまして、その中に雑多な品(手技療法、徒手療法とよばれる施術法)が入っているわけです。
マッサージのような揉みほぐし的なものや、骨盤矯正やら筋膜リリース、ボキボキ系やら非ボキボキ系。
はたまた〇〇式整体、〇〇療法、〇〇術やら独自に開発した手技?など古くからあるものから新しいものまで多種多様ですね。
これ、一般の方に個々の手技を説明しても分かりにくいでしょうし、興味もあまり持たれ無いでしょう。
ですので「整体」に括ってしまうのが簡単です。
まぁ逆に言えばこの為、整体と一口に言っても施術者により手法が似通ったり、バラバラだったりしますので余計に分かりずらくもなっていますが…はい。
と、いう訳で当院でも「整体」として括っております。
実施致します個別の手技手法に関しましては名称のついているものから、経験上身に着けました我流のものまで幾つかあります。
しかし名称のついている手技を話したところで世間には認知されていませんし、却って分かりづらいかと。
認知されている(?)整体と表現した方が伝わりやすいでしょう。
その為、同じ整体を名乗っていても施術方法は違っていたりする訳なんですよ。
なんとなくお分かり頂けたでしょうか?
追伸
時々、You Tube番組で整体施術者orカイロプラクティック施術者の方に「カイロプラクティックと整体は何がどう違う」と質問されるシーンを見かけたりします。
質問者の方はどちらもボキボキ?矯正するようなイメージをお持ちなんでしょうかね?
それで違いがわからないと。
いや~「カイロプラクティック」はアメリカ発祥の手技療法のひとつの療法名であり、整体は属性名ですから比較する論点が全く違っています。
〇〇式整体や〇〇式手技とカイロプラクティックの違いは?でしたら正しい比較論になりますが。
類似した質問に「マッサージと整体の違いは?」というのもありましたね、これも同じです。
【結論】
整体という言葉は何気に認知されて来ているかとは思いますが、実体はこのように統一されているものでは無く、属性の名称を表す言葉と捉えて頂くのがよろしいかと思います。
実際のところは、施術者に確認されるか施術を受けて判断されるしかないのではと思います、はい。
東洋医学(的)か?
整体は東洋医学のジャンルに含まれると勘違いされている方もいらっしゃるかも知れませんね?
いぇ、整体は東洋医学ではないんですよ~。
たしかに整体にも東洋医学的(?)な手技ももちろんあります(日本で出来た手技、それぞれ名称はあります)が。
基本的には別物。
日本で東洋医学といえば大別しますと「漢方(薬)と鍼灸」でしょう。
しかしややこしい事にもうちょっと細かく述べますと以下のように分類される事でしょう。
●東洋医学概念に基づいた漢方薬治療
●現代医学的?概念(診断、疾患名)による漢方薬治療
●東洋医概念に基づいた鍼灸施術
●東洋医学概念とは別の概念に基づいた鍼灸施術
なんだかよく分かりませんかね?
そうですよね、漢方や鍼灸などは現代医学のジャンルでは無いので東洋医学だと思われる事でしょう?
では東洋医学といえるのは何かと申しますと、上記しました通り東洋医学概念(例えば陰陽五行、虚実、五臓六腑など)を基に、東洋医学独自の診断法(脈を診たり、腹を触って診たり、舌を診たり、身体を触ってみたり等)を用いて「証(しょう)」という独自の診断を下して処方や施術するということです。
漢方薬処方で例を挙げますと「風邪に葛根湯」のような処方は現代医学的な処方の仕方となります。
一般的に病院などを受診して処方される漢方薬はこのような形となりますでしょう。
東洋医学独自の処方となると漢方専門医の医師か薬剤師以外では難しいでしょう。
もっとも軽症の場合や複雑な症状でなければ現代医学的処方で効果がみられることも多々あるかも知れません。
鍼灸施術の場合は施術者により十人十色と云われる位ですのでまちまちでしょう。
どのような施術法が良いとか優れているかは中々判断出来ませんね、それぞれといったところでしょうか?
全体的には東洋医学に基づいた鍼灸施術を行っている施術者は少ないと云われているようです。
一般の方には何がどう違うのか…これまた分かりづらいでしょうね…はい。
では、マッサージはどうなのか?と。
これはカタカナ表記されている位ですので西洋(ヨーロッパ)発祥の手技療法のひとつです。
日本版のマッサージ?といえるものに按摩(あんま)と指圧があります。
按摩は原型としたは古代中国より伝承し日本で変化していった手技ですし、指圧は日本で発祥し基本、押すことを主とした手技です。
これらを東洋医学に含むものとしているのかはワタシは存じませんが…。
まぁ何にしてもですが、どのジャンルのものであれ有用(害が無く、役に立つもの)であれば賢く利用されるのがよろしいかと思います…はい。
原因は?
原因は一つだけと思っていませんか?
この症状が起きるのはこれが原因だって。
確かにそれの方が分かりやすくって良いですよね。
その原因さえ取り除けば解決。
しかしどうなんでしょうか?
慢性的であちこち具合がよろしく無いような場合、一つの原因に絞りきるのはちょっと難しいかもしれません。
また回復力の差などはご自身の体力やら生活習慣やら環境やらと何かと影響を及ぼすものがありますので皆が同じではありませんよね。
「〇〇を行えば~」「〇〇を食べれば~」とは行かないケースが多いでしょう。
ワタシの場合、原因という言葉を使うのがあまり好きでは無く、「要因や要素」という表現を使うことが多いです。
複数の要因や要素が重なり合ってその症状が引き起こされると考えますね。
例えば「ギックリ腰」でも、「重い物を持ったから、腰を捻る動作をしたから」などはきっかけ(つまり一つの要素)であり、既に腰などが良い状態では無い、実は疲れが溜まっていた…などなど複数の要因がありぎっくり腰になった…と。
よく聞く話で「年齢(加齢)のせいで~」やら「軟骨が減って」なんて言われる事もありそうですね。
いえ、確かに加齢も大事な要素であるのは間違いありません。
10代やら20代の時と比べると体力も免疫機能も低下しますし、基礎疾患を持っている可能性も高い、長年の疲労の蓄積もあるでしょう。
軟骨も減ってきますし。
しかしこれらは要因、要素の一つであって全てではありません。
複数の要素が重なり合わないと症状は起きにくいでしょう。
結論的にいえば重なり合う要因、要素が多ければ多いほど症状も複雑化しやすく、改善に手間取り長引きやすい。
少ないほど改善、回復しやすい可能性が高いと言えるのではないでしょうか。
整体界隈では良く聞かれる事も多いと思いますが「背骨の歪みが~」「骨盤の歪んで~」「筋膜、筋肉が~」「姿勢が~」なんてフレーズ。
確かに全て大事で原因とも云える要素ですが、逆に言えばそうなっているのも結果でしかない…とも言えそうな気が?
また「原因は患部では無く、別の場所にある」的なフレーズもよくありますね。
「腰が痛いのは腰に原因があるのでは無く、〇〇に問題がある」なんて。
これまた確かにそうワタシも思います。
実際、脚(足)やらお腹側の筋肉などの問題が影響していたりと。
(患部にも問題はありますよ、この場合は腰そのものにもです)
ただこのように腰痛でも肩こりでも患部だけでは無く、他の場所からの要因、要素が絡んで来るわけです。
肩こりでも手指、手、腕だったり腰や脚からだったり…です。
また喰いしばりやらストレスやら、食べすぎやら睡眠不足やら何やらと要因、要素が重なり合うわけです。
その複数の要因、要素を減らす(解消)事が必要ですね。
ワタシの場合、施術方針はその要素、要因をちょっとでも減らそうと考えアプローチするだけです。
時折お見かけする「根本原因?を~」なんて考えたことは無いですね~。
読める身体
「読める身体」ということで…。
これワタシが勝手に言っている事ですけど。
通常、施術にあたって先ずはカウンセリング(問診)や検査などが行われると思います。
当院でもそうですね。
それらはもちろん大事な事ですが、実際は施術しながら分かる事はそれら以上にあったりしますね。
まぁ、ワタシの場合は…ですけど。
読む身体というと能動的に行う感じですが、どちらかというと受動的に施術中「ここに問題があり、問題が起きている」みたいな解決の為の糸口が分かってくる…のような感じでしょうか?
もちろん初回からそうなる場合もありますし、2~3回以上の施術が必要な事もあります。
しかしどなたに対しても同じように読める訳では決して無く、これが「読みやすい(読める身体)方」と「読みにくい(読めない身体)方」に分かれるんです。
もちろんどちらにも幅があって「けっこう読める~まぁまぁ読める」のような感じで「読みにくい」場合も同様です。
で、当然読みやすい場合の方が施術効果と申しますか変化がおきやすい。
逆の場合はなかなか難しい。
これは手技のみならず気功でも同様です。
はっきりと強く気の滞っている感じがワタシの手のひらに痛みや圧力?のような感じで伝わってくる場合の方が変化が良いですね。
ところで、どうして「読みやすい(読める)」「読みにくい(読めない)」に分かれるのか?
これははっきりとはわかりませんが以下のような事でしょうか?
①ワタシの技量不足
②現在現れている症状は別の疾患などにより引き起こされている場合(例えば腰痛の原因が別の疾患が原因で起きている…など)
③その方の内面に例えば強いストレスやトラウマ的な問題などが存在していて回復を阻害している?など。
う~ん、他にもあるかもしれません。
もっと読めるように研鑽しなくてはと、反省です。