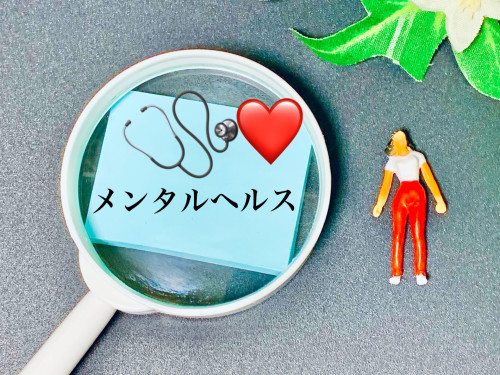ブログ
あやしい水商売?
といっても「〇〇水」などの水の話ですけど。
ワタシが知る限りでも、もう30数年前以前から既に存在してましたね。
何とかの高額浄水器やら整水器、活水器など商品が。
〇〇水で言えば、アルカリイオン水や酸性水、πウオーター、創生水、磁化水、電子水…などなど。
以前は一般向け書籍(効能効果や体験談など記載されていました)や健康雑誌の広告などありましたねー。
おそらく「バイブル商法」になるのではないでしょうか?
しかし中には驚く事に現在も販売されている商品(整水器)もありますので凄いですね~。
昨今でしたら水素水、最近ではシリカ水などでしょうか?
ネット上にも良く紹介されていたような…。
薬機法や景品表示法などにより効能効果などはあまりおおっぴらには謳えません
たしかに水は生体を維持するのに必須ですし、体内の約60%を占めるとかなんとか、そう思うと大事なものですけど。
しかしこれらの特殊な水はいかがなものなんでしょう?
使用された方の目的としては水の味?(まろやかさ)やら安全衛生面、健康維持増進やら美容目的、あるいは治病目的など様々おありでしょう。
ただ治病目的に期待されるとかなり難しいのでは無いでしょうか?
基本的に治病効果は専門家の間では完全否定されていますし、国民生活センターからも注意喚起されていますのでね。
ただ幸か不幸か基本、水なので飲んでも健康被害が無いw。
ついでに効果も無いw…のかなぁ?
実際、これらを飲まれていた方(いる方)にお話しを伺ってみたいものです。
いやワタシも実は昔、これらのバイブル商法的な本を読んでちょっと興味をそそられた口です。
「なんか凄そう~」「欲しい~」
なんて思いましたが高額なので買いません(いや買えません)。
水に高いお金を使うなんてあり得ない!はい、そんな感じでした。
そんなワタシでしたがその後、磁化水器なるものを購入したことがあったんです、まぁまぁ購入出来る金額だったので(2万弱)。
強力な磁石を蛇口に挟み込み使用する簡易的なタイプのものでして、理屈としては水がその磁石の間を通過する際、その磁力により活水化されるとかなんとか…?
いやぁ今考えると馬鹿ですねー。
蛇口の水なんて物凄い速さで通過するのに磁石を通過する際に磁力でどーたらなんてある訳ありませんよねぇw.
ファンタジーですね!
それに引っ掛かりました!
奇跡の水?はきっとないでしょう、おそらくね。
皆様も何かしらご購入を考えていらっしゃるのでしたら、ご自身の目的にあったものか良く調べてから検討された方が良いですよ。
水道水のカルキ臭やカビ臭、ちょっと安全面が気になる、まろやかさが欲しい…などの場合でしたらホームセンターで市販されている安価な浄水器で十分すぎるでしょう。
まぁ、カートリッジ交換のランニングコストはかかりますけど…。
ミネラルウォーターを買い続けるよりはお得ではないでしょうか?
くれぐれも訪問販売やマルチ商法のバカ高いような浄水器、整水器などにはご注意を!
そういえば以前、アトピーに効くみたいな触れ込みで浄水器でしょうか?勧めるアトピービジネスってありましたね。
詐欺っぽいビジネスってわりとありますよね。
あ、われわれの業界でもアトピー整体?の触れ込みの施術院さんがあるらしいですけど大丈夫なのかなぁ??
心配。
こころの風邪?
前回のテーマが”五月病”でしたので、その繋がりのテーマをちょっと。
あ、もちろん専門家ではありませんので浅くてスミマセン…。
ところで”うつ病はこころの風邪”ってキャッチコピー、記憶にあります?
10年ちょっと前でしょうか、”うつ病”に対して盛んに言われてました。
おそらく、この意味は風邪のように誰でもなる可能性はあるという事でしょうけど、風邪のように大したこと無いと誤解された向きもあったとか?
それで批判も起きた為、その後あまり使われなくなったのでしょうか。
その為、”うつ病はこころの骨折”と唱えた方がいらっしゃるようですね。
なるほど、確かに誰でもなる可能性もあるし、放置しておくと大変なことになるのできちんと治療を要すると云う意味では的を得ている感じです。
【こころの病】
身体的な疾患や症状と比べると、より分かりずらいですよね。
血液検査や画像検査だったりで数値化したり変化が見られる訳でもないですから。
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、神経症性障害(不安神経症やパニック障害等)やら統合失調症、昨今よく聞く発達障害…などなど。
当事者やその周辺の方、関係者以外には馴染が薄いですのであまり理解されにくいでしょうし偏見を持たれる可能性もありそうですね。
ワタシもお会いしたことがあるのはうつ病(軽症で安定した状態)の方と神経症性障害の方だけですので後は全く存じ上げません。
【うつ病】
こころの病の中でも一番多く罹患されているのがうつ病のようですね。
人間ですから誰しも落ち込んで元気が出ない、憂鬱状態は経験はあるでしょう←これを「抑うつ状態」と言うそうです。
ワタシも数え切れずに腐るほどあります。
その抑うつ状態のひどいのが1日中ずーっと続いたりするのは、しんど過ぎますね。
あるいは喜び感や何事にも興味を持てなくなったり、思考や集中力が低下したり。
自分を責め過ぎたり、自己否定が強くなったり不安感、イライラしやすくなったり。
悲しみ(涙もろくなる)や反応が鈍くなったり…などなど様々な精神症状が起きる場合が多いようです。
(個人により症状に違いがあります)
また様々な身体症状も起きやすいようです。
頭痛、頸肩こり、腰痛、便秘、睡眠障害(不眠や過眠)
食欲障害(食欲減退や増加)体重の変化(体重低下や増加)
倦怠感、疲労感、動機、息切れ、めまい、腹痛…などなど。
身体症状だけだと普通に身体の疾患となってしまいますが、上記のような精神症状が伴っているとうつ病と診断される可能性があるようですね。
ところで、このうつ病ですが(もちろん他の疾患も)現在でもハッキリとした原因は分からずいくつかの仮説がある状態とのこと。
そりゃ先述しましたけど目視出来たり、触ってみたり検査で数値化出来たりしませんから分かりにくいですよねぇ、こころや脳内って。
ただ基本的な要素として以下のようなものが複合要因としてあるようです。
●過度あるいは継続した何等かのストレス
●それらのストレスによる脳内の変化
●個人の性格的特性
●遺伝的素因
人間ですから、生きてりゃ何かと悩みも尽きない…。
大小様々なストレスフルフル。
病気にもなりそうですよね。
しかし実際、病気にまでなる場合とならない場合がある訳ですから結局、人それぞれと云うことでしょうか。
【治療と予防】
結果、うつ病になったとしたら治療は薬物療法、休養、心理療法(認知行動療法など)が行われるようですが、心理療法などを行っている医療機関は実際少ないようで専ら薬物が主体になってるようですよ。
病気になってしまうと、もちろん辛い。
ですのでなるべく予防的措置?を取りリスクを減らしたいものです。
例えばですが、仕事で過重労働などやハラスメントなどで問題があり改善の余地がなければ自分から逃げる(退職など)選択も必要でしょう。
ちょっと大変ですがこのように環境を変えるのが有用、必要な場合もあるでしょうし。
そういった場合でなければ自身でのケアが必要でしょうか。
メンタルへのアプローチ法で例えば呼吸法、瞑想、マインドフルネスなどのようなものもありますが特殊過ぎて誰でも行えるものでは無いし難しいですね。
ですのでもう、基本中の基本のこれまた当たり前過ぎてツマラナイかも?ですが日常生活を整える。
睡眠、休養、適度な運動(医学的にもかなり有用と云われます)食事などを見直す結果、ストレス反応が弱まったり、耐性が強まったりする可能性があるようですよ。
身心の健康生活の基本ですよね(医学的にも)
また東洋医学では心身一如と云われたりします。
こころへのアプローチは難しいので身体へのアプローチを行い、こころへの調整を行う感じでしょうか。
この考え、わりと有用とワタシは思います。
もちろんある程度の効果になってしまいますが。
あとワタシ的にお勧めなのが、ノート記入です。
色んな鬱屈した思い、吐き出したいでしょう。
なかなか人に聞いてもらうのも難しいし場合によっては面倒な問題になってしまうこともあります。
そこでノートにストレスを感じた出来事や対人関係、感情や鬱屈とした思いなどノートに向かってぶちまけるように書き殴る、といった手法です。
気が治まるまで何回同じことを書いても、どんな乱雑な字や文章の形など気にすることなく発散させます。
何回でも行っているうちに、少し冷静になり自身を振り返り内省出来るようになるかも?です。
ぜひ、お試しあれ。
【当院では】
別に「うつ病~」などと全く謳っておりませんが、「自律神経~」とは謳っている為でしょうか?
たまに軽症うつの方(病院に通院中で薬物療法を行っている患者さん)が不眠傾向や身体の鈍痛(頚肩や背中の痛み、腰痛など)でお見え頂いたことがあります。
ですが特別、大元のうつ病そのものに対してアプローチなどは致してはおりません。
あくまで症状緩和の施術をしておりますので、はい。
メンタル的な問題って難しいですね。
”うつ”と迄は行かなくても、日々のストレスや感情に流されたり思考のあり方によって体調を崩したり様々な方面に影響を及ぼします。
”病は気から”ですね。
お大事に。
五月病って?
昔から「五月病」って言葉がありましたけど、今でもやはりこの言葉、あるんですね。
先日、たまたまTVの報道番組を見ていましたら特集されてました。
GW明けあたりが丁度、五月病のシーズンなんでしょうか?
幸いなことに、ワタシは五月病と呼ばれる状態にはなったことは無いので実体験は語れませんが。
まぁワタシも学生時代や勤務時代は年末年始やGWなどの連休の終わりが近づいて来ると「学校行きたくないー」「仕事めんどー」「もっと休んでいたいー」なんていつも思っていましたがw。
幸か不幸か、今ではGWなんて無い生活になってしまいましたw
(極超零細個人事業のため)
話を戻しますと、この「五月病」という言葉はあくまで俗称です。
医学的に云うと「適応障害」と呼ばれる診断名がつくことが多いそうです。
適応障害って以前、現皇后陛下の雅子様にも付けられていた診断名ですよね?
これは”新しい環境に適応出来ないことがストレスになり心身に不調が起きて生活に支障が出る状態”だそうです。
新入学や新社会人、新しい部署、引っ越し、付き合う人間関係や生活スタイルの変化などが新年度になると起こりやすいですので大変ですよね。
丁度1か月位が過ぎ、GW辺りにガクッとなりそう。
身体面の不調としては全身倦怠感や疲れが取れにくい、食欲不振、寝つきや寝起きが悪い(不眠傾向)、めまい、動悸、肩こり…などなど。
精神面の不調としては気分の落ち込み、意欲が湧かない、集中力低下…などなど。
適応障害と似たような症状を来す疾患としては他に「うつ病」などがありますが、一般的には適応障害は一過性、比較的短期間で済むケースが多いようですがうつ病はもっと長期間に渡り、また症状も強く出るケースが多いようですね。
適応障害は環境に適応出来ないことがストレスになりやすい訳ですから、環境を変えると改善が見られる場合が多いようですがうつ病の場合はあまり関係が無い場合が多いようです。
とはいっても適応障害と思われていたら、実はうつ病だったケースもあるとのことですし、適応障害がこじれてうつ病になってしまうこともあるそうなので注意が必要ですね。
他にも特に未成年者の場合、類似した症状を来す疾患としては「起立性調節障害」と呼ばれる疾患もありますので鑑別が大事とのことです。
(この疾患ですが大人が場合も、もちろんあります)
しかしこれらの症状はなかなか辛いですね。
といって自己判断で精神的な疾患と早急に決めつけずに、特に身体面にも不調が起きているなら、まずは内科等の診療科を受診して内科的な疾患が無いか検査を受けましょう。
精神的な疾患かと思っていたら実は身体的な疾患だったというケースもありますので。
それで特に身体的疾患が無いようであれば心療内科等を紹介して頂いた方がよろしいかと思いますよ。
ところでまた話はちょっとそれますが、先日たまたまTVを見ていたら「退職代行サービス」の企業が取り上げられていました。
いやぁ~これ、なんか凄いですね。
以前でしたらあまり考え付かないサービスですよね?
このサービスの是非はともかく利用する方の気持ちも分からなくも無いですが…。
仕事辞める時ってどうです?
入ったばかりの職場を辞める時や責任感が強い人、なかなか辞めたくても辞めさせてくれない職場、ほんとの意味でのブラック企業…。
けっこう辞める時ってちょっと緊張したり、大変だったりしません?
ワタシも複数個所の職場を辞めていますので、辞めたい申し出をする時はやはり緊張しましたね。
言ったあとはさっぱりしましたけどw
ところで仕事を辞める理由なんて様々な理由がありますので個人の問題であり、また自由なことですが中には自分の思っていた理想と現実が違うので辞めるとか条件が提示されたものと違っていたから速攻辞めるなんてケースの場合もあるようですけど、こんな場合はどうなんでしょう?
あまり早く見切りを付けてしまう事で後々失敗してしまう事もありますし、それが良かったという場合もあるでしょうけどある程度の期間はその仕事に取り組んでみてからでも遅くは無い気もしますが…?。
ホントのブラック企業やブラック上司の場合でしたらは速攻、辞めたほうが良いかもですね!
退職代行サービスにお願いしましょうか?
免疫って難しい
免疫って言葉、よく聞きますね。
特にコロナ禍になってからでしょうか?
しかし免疫ってなに?
となると良く分かったような分からないような…。
ええ、ワタシも良く分かりません。
だいいち免疫に関してはまだまだ解明され尽くしたわけでは無い…とのことですし。
そんな訳ですから小難しい内容は研究者の先生方にお任せするとして、ワタシ達は「ウィルスや細菌、カビ、寄生虫などの異物から身体を守るシステム」位知っていれば十分かと、はい。
結局、ワタシ達にとって肝心なのは理論理屈より免疫が正しく機能していることかどうかということですからね。
【免疫あるある?】
巷に出回っている免疫に関しての内容で実は正しいかと思っていたことが、どうやらそうでも無いということが多いらしいですよ、ご存じでした?
「免疫力」
この言葉よく聞きますけど、実は医学的には無い言葉で誰かの造語とのことです。
誰が造ったんだろう?
一般的にはこのワードは馴染があって、免疫の力って何となく伝わりやすい気がします。
造った人、凄いですね。
まぁ、正しくは無いですけど。
「免疫力UP」
免疫力を高めるということで「〇〇をして免疫力UP」「〇〇を摂取して免疫力UP」なんてフレーズ、よく聞きませんか?
しかし、これは曲者ということですよ。
なぜなら免疫ってごく一部に関しては測定出来るものの全面的には現在、測定不可だそうです。
ってことは、安易に「これで免疫力が~」は推測?適当?嘘?〇〇販売の為の宣伝?ということになっているということで、はい。
断定的に”これで免疫力を~”と言われるといかにもホントのことと思ってしまいますが、実は科学的根拠が無いそうですよ。
そもそも免疫って高めるとか何とかでは無く、適切に機能しているかどうかということだそうです。
「体温が高い方が免疫が強く、低いと様々な疾患に罹りやすい」
これは以前、肩書がある大学教授が言い出しっぺで、それが一般的に広まってしまいました。
ワタシも当初からこの説は知っていまして、信じていた時もありました。
平熱は高い方が良い…ということでしたので、ひょっとすると”温活”が叫ばれたのもこの説がベースになったのかも?しれませんね。
しかし、これも根拠が無いということで免疫どうのこうのは、はっきりしていないとのことです。
そうですね、ワタシも勤務時代は患者さんの体温をチエックする機会が多かったんです。
ですが平熱が36,5℃以上ある方でも大病を患っている方は多くいらっしゃいました。
逆に35℃代でも90才を過ぎても割合、元気で大した病気もしていない方もけっこういらっしゃいましたのであまり関係ないかもですね。
ちなみに「お風呂に使ったり」「白湯を飲んだり」「ショウガを食べたり」などの”温活”?しても平熱は上がりませんよ、もちろんお分かりの通りお風呂などに入ればその時は体温は上がりますけどその場だけでしょ。
【免疫機能を低下させる要因は?】
これは「加齢」「過労」「疾患(例えば糖尿病やがんなど」「ストレス」「不適切な生活習慣(睡眠や運動、食事など)」など。
いやぁ、普通と言いますか当たり前過ぎて面白味が無い…。
逆に言えば免疫機能を適切に機能させるにはこの逆を行う。
加齢はどうしようも無いですけど、つまり何か特別な事や方法では無く当たり前のように健康を意識した生活習慣を行うということだそうで、はい。
ですから現時点では世に出回っている「これで免疫力が~」と叫ばれている物や方法などはちょっと冷静に見た方がよろしい様ですね。
ま、ワタシ個人的には身体に害が無く、変に高価などでは無く、身体にとって良さげな事であれば免疫とか考えずに試してみるのもアリかな?
とは思いますけど。
あ、そういえば思い出しだのですがコロナ禍の最中、ある施術院さんの店舗前にA型看板が置いてあってそこには”整体(か何か)で免疫力UP”のようなことが書かれていましたがこれはダメでしょ、はい。
変形性関節症
変形性の関節症ってありますよね。
あ、背骨や関節の「歪み」などではありませんよ。
あの「軟骨がすり減って~」などで有名なやつです。
特に膝と股関節が有名ですかね?
もちろん他にも手指、肘、肩、足首、背骨などもなります。
最近有名?になって来た手指が変形して曲がってしまう「へバーテン結節」や頚椎(背骨の頚の部分)ですと「変形性頚椎症」、腰椎(背骨の腰の部分)ですと変形性腰椎症などの診断名がつきます。
関節などの変形を引き起こす要因としては「加齢」「酷使」「怪我」「遺伝性」などが上がられています。
で、変形したもの(すり減った軟骨や椎間板など)は戻るのか?
はい、残念ながら減ったものは通常は戻りません。
お薬を飲んでも、整体や東洋医学なども当然無理。
ヒアルロン酸注射や”軟骨成分サプリ”なども無理ですね、戻りません。
今後、再生医療が進めば減った軟骨なども戻るようになるかも知れませんね?
では、痛みや不具合はどうしようも無いのか?というと今のところ、主原因が関節にあり、比較的重度の障害で日常生活に問題が生じている場合は手術以外ないでしょう。
もっとも重度になってからでは無く、ある程度の段階で手術をした方が予後(その後の経過と結果)が良いとされています。
しかしそれ程では無い状態、症状でしたら保存療法(手術以外の方法)でも改善、緩和、進行を遅らせるなどの余地はあります。
日常生活の工夫や運動や我々のような施術などですね。
実際、レントゲンなどで軟骨などの変形が確認されている方でも無症状の方は多くいるとされているようですし、変形があって痛みなどの症状がある方でも不調の要因が関節(例えば膝関節痛)以外の部位にあったりした場合はそちらにアプローチすることにより緩和する可能性があります。
ですので一概に変形しているから、軟骨がすり減っているからと諦めずに色々な改善の為の選択肢を持っていただきたいです。
あ、繰り返しになりますが”軟骨成分〇〇”は無理ですから。
コラーゲン、ヒアルロン酸(サプリ)、コンドロイチン、カルシウム、サメ軟骨など…いや無いですね~。
最後になりますが膝や股関節の変形性関節症に脚を持ち上げたりする筋トレが推奨されていますが、それはそれで良いのですが忘れてはいけないのが関節可動域を保てるようにすることですね。
これ、わりと忘れがちです。
うっかりしていると関節が固くなり気がつくと可動域が狭くなってしまった人がいらっしゃいますよ。
例えば膝なら、まだ痛みが左程でも無く関節可動域がある方ならしっかりと最大限に曲げたり伸ばしたりと毎日動かして下さい。
動かすと痛みが出たり、ちょっと関節の動きが固くなって来た方は痛みの出ない範囲で無理のない範囲で最大限に少しずつ毎日行い、徐々に動く範囲を拡大して下さい。
あせらず、毎日コツコツと長期戦ですね。
あと膝や股関節に問題のある方は「歩けなくなると大変だから」とウオーキングなどをがんばってしまう方がいらっしゃいますが、ほどほどに歩きましょう。
毎日歩かなくてはいけないとか、何歩あるかなくては、何時間歩くなど決めつけずにその時の状態で判断した方が良いですよ。
かえって負担を掛け過ぎて痛みなどが出てしまう方もいらっしゃいますのでね。
また歩くことだけで運動は良しとしないで下さい。
関節可動域の訓練にも筋トレにもウオーキングではなりませんよ。
なんにしても早めの対策が肝心ですね、以上です。